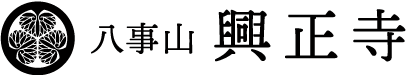人生の節目とお寺は密接な関係があります。
安産祈祷から始まり、初寺百日参り(蟲封じ)、七五三、十三参り、合格祈願、厄除け祈祷、仏前結婚式、先祖供養、お葬儀、永代供養と。
興正寺では生まれる前から亡くなった後まで皆様に寄り添い、共に歩み、すべての節目をお寺で過ごしていただけるように勤めさせていただきます。
目安ご出産前
仏教の世界では偶然はなくすべて必然ととらえます。私たちの命は親から授かり、その親も互いの親からと多くのご縁が繋がり続いてきた命の末端なのです。安産祈祷は安産守護の仏様「大隨随求明王」を本尊に迎えて、次の世代にご縁を繋ぎ子供が無事にこの世に生れてくることを願う祈祷です。
犬はお産が軽く多産であることから戌の日に行うことが多いようです。

目安0~一歳
お子様が生まれてから百日を目途に首が座り落ち着いてきたら仏様に無事に生まれてきたことを報告するとともに感謝をするのが初寺百日参りです。その際に蟲封じの祈祷をさせていただきます。
蟲とは赤ちゃんが生まれてくるために必要な細胞のことで、生まれてからは癇癪や夜泣きの原因となると言われています。その蟲を封じる祈祷をし、感謝の供養を勤めます。

目安三~七歳
三歳・五歳・七歳と子供がその歳まで無事に成長できたことを感謝し、子供の長寿と幸福を願う祈祷です。昔は三歳を「髪置」五歳を「袴着」七歳を「帯解」と呼び節目節目に仏様に手を合わせていました。
幼い頃から、見えないものに手を合わせ多くのご縁に感謝する心を育む大切な行事です。

目安十二~十三歳
満十二歳は数え年で十三歳にあたり干支が一回りして初めての厄を迎える年にあたります。その厄を払い福徳と智慧と健康を虚空蔵菩薩に授けていただきます。この虚空蔵菩薩とは智慧の仏で真言宗の開祖「弘法大師空海」も熱心に拝まれ、見たもの聞いたものを忘れなかったと言われております。

合格祈願と聞くと進学するための受験を思い浮かべる方が多いと思いますが、それだけではありません。資格を取るための試験なんかもあったりします。ただし合格祈願を受ければ必ず受かるわけではありません。仏様は努力をしている人に対して最後の一押しをしてくれるそのご縁を結ぶのが合格祈願になります。

「人は星のもとに生まれる」こういった言葉があります。私たちは生まれた年によって自身の「本命星」という星が決まります。そして毎年「当年星」という星があり、自身の星と、その年の星の兼ね合いで私達の吉凶が決まります。自身を守るためのお札や御守りを祈祷して授与させていただきます。

運命の赤い糸は生まれた時から結ばれている。その赤い糸を固く結びつけ仏様とご先祖様に報告をする儀式です。ご先祖様やご両親、ご親族、ご友人の前で結ばれるご縁に感謝し、僧侶の司式に則り、式を進めてまいります。最後に戒師様より夫婦の在り方を説いていただきます。

お葬式とは、『葬送の儀』と『告別式』の二部構成になっており『葬送の儀』では仏弟子としての戒を授かり(授戒)、名も戒名(法名)に改め浄土へと旅立っていただきます。次に『告別式』では故人との最後のお別れをしていただきます。通夜は遺族の為、告別式は一般の方のお別れという考え方もあります。担当になった僧侶からお葬式のことや、これからの仏事のことを一から丁寧にお話しさせていただきます。

「供養」は供え養うと書きます。この養うという字は二つに分けることができます。「美しく良い」です。美しく良いものを供えるとは一体何か。それは故人へ思いを馳せることだと思います。その大切な思いを僧侶の読経をもって届けさせていただきます。毎月の命日や彼岸、お盆、回忌などのご供養も承っております。

永代供養とはお寺がお施主様に代わりお寺が続く限りご供養していく事です。男子が無く自分の代で絶えてしまう方や、近年では子供に迷惑をかけたくないとの思いで申し込まれる方もございます。興正寺では納骨堂と永代供養が一緒になっている物もございます。